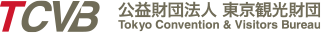三好 崇弘のプロフィール

| 氏名 | 三好 崇弘 (みよし たかひろ) |
|---|---|
| 団体名 | 有限会社 エムエム・サービス |
| 役職名 | 代表取締役社長 |
| 上記以外の勤務先 | 特定非営利活動法人PCMTOKYO監事役 グローカルな仲間たちGLFP.JP主催 |
| 派遣地域 | 23区 島しょ部 |
|---|---|
| 対象地 | 街・繁華街 中山間地域 |
| 専門領域 | 計画策定 組織・人材・財源 インバウンド |
| 地域との関わり方 | 地域密着型 専門特化型 総合型 |
| アドバイスの仕方 | メッセージ型 協働型 |
自己PR、団体・地域等へのメッセージ
観光まちづくりには多様な関係者の協力が必要です。時には変わることも必要ですが、「人は他人から指摘されても変わらない。自分で気づき、体験したことでしか進めない」というのが現実ではないでしょうか。
私はこれまで20年間、海外30か国以上での国際協力で貧困や経済発展についてのアドバイスをしてきましたが、その中でも、ザンビアで9年間、数にして500村(35万人)の地域づくりをした経験から上記を強く信じるようになりました。その思いや経験を国内の地域づくりにも活用することで成果を生んでいます。
各地域は表面的な課題は同じですが、その原因は地域ごとに違い、動的(留まらない)です。他地域の解決策のマネ(模倣)では根本的な解決にいたらないどころか、地域が疲弊する原因にもつながります。
地域の課題は地域の人が自分で気づくことが大切で、また解決策も自分で見つけ出すことで実践につながります。ただ、地域の人だけでは不十分で、ヨソモノを取り込むことが必要不可欠です。
そのためには「参加型」「協働型」とよばれる手法が効果的です。参加型とは、課題に関わる人たちが主体的に課題に気づいて、分析し、解決策を見出し、進みだすための方法やその道具たち。
地域主体の「参加型」で地域づくりを進めていき、ともに歩むアドバイザーでありたいと思っています。
専門分野
観光まちづくりに関する主な実績
| 事業名 | 依頼者 |
|---|---|
| 千葉県山武市における地方創生戦略づくり (2015年) | 山武市 |
| 式根島(東京諸島)における観光まちづくり10年戦略 (第一フェーズ 2015年)(第二フェーズ 2018年) | 東京都式根島 |
| 海外人財を活用した式根島(東京諸島)における参加型の地域資源発掘調査 | 一般財団法人海外産業人材育成協会 |
| 宮城県丸森町における海外人財(ザンビア)を活用した地域づくり(2015年〜2018年) | 丸森町耕野まちづくりセンター |
| 福島県南会津町における地域づくりリーダー養成事業(第一フェーズ 2015年)(第二フェーズ 2018年) | 南会津町 |
| 東北地方における復興後の地域づくりをになうNPO人材育成事業 (2017年) | JEN (NPO) |
| エジプト・オールドカイロにおける旧市街歴史遺産を活用した地域づくり (2016年〜2017年) | トヨタ財団支援「ベイト・ヤカン」プロジェクト |
| 中之条町美野原地区における農業担い手育成事業 | 群馬県中之条町 |
| 南会津町における関係人口創出アドバイザー | 福島県南会津町 |
| 松田町の耕作放棄地を活用した新しい観光産業の在り方 | 神奈川県松田町 |
これまでにアドバイザー等で深く関わった地域、現在、活動されている地域と、その概要
| 市町村名 | 取り組みの概要 |
|---|---|
| 群馬県中之条町 | 中之条町は農業では様々な野菜が生産されており、四万温泉に代表される観光資源も豊富であるが、それぞれの資源がばらばらに点在しており、つながりがみえずに相乗効果をだせずにいた。そのため、各生産者と地域の事業者を有機的につなぎ、地域経済振興のためのバリューチェーンと新しい組織をつくることになった。コロナ禍であったが、多くをオンラインに切り替えることで、反対に全国レベルに活動を広げ、海外のシェフともつながるなど、グローバルなつながりを創出した。 |
| 福島県南会津町 | 福島県南会津町は高齢化や人口減が深刻であり、再活性化や再編成が必須となっていた。その中で、関係人口を創出して、地域の課題をともに解決するための人材育成をする必要があった。コロナの状況を受けて、オンラインを通じて、全国とつないで、若者を中心に、地域づくりの勉強会やオンラインツアーを実施。若者が地域を訪れて地域の課題をともに考え人財を育成する仕組みをつくった。 |
| 東京都式根島 | 式根島は年間3万人弱の観光客が訪れる観光地であるが、地域の人口減少と高齢化が進み、観光がまちづくりにつながっていない。地域の資源は豊富であるが十分に活用されておらず、また地域住民の参加も不十分である。そのため地域の観光とまちづくりが融合するための中・長期的視点からの戦略をつくることを目的として、参加型ワークショップを中心とした戦略づくりを実践した。 |
学歴・職歴等
| 学歴 | 日本大大学院修了(政治学修士)、英国マンチェスター大社会経済学部大学院修了(経済学修士) |
|---|---|
| 職歴 | 1992年~2002年株式会社福山コンサルタント(海外事業部) 2002年~2004年財団法人国際開発高等教育機構(現一般財団法人国際開発機構) 2005年有限会社エムエム・サービスを設立、代表取締役として現職 2017年~宮城大学(客員教授) 2021年~放送大学(非常勤講師) その他、琉球大学、横浜国立大学、龍谷大学、慶応大学、アジア太平洋大学等で非常勤講師など歴任 |
| 著書・論文・講演等 | 2003年11月「新しい政策プログラム評価手法"LEAD"の紹介」日本評価学会第四回全国大会論文集 2004年10月「PCM-I(プロジェクト・サイクル・マネジメント・インプルメンツ)」NPO法人PCM-Tokyo 2005年3月「キャパシティ・デベロップメントからみたJICA技術協力の有効性と課題に関する一考察」国際協力機構 2007年4月「参加型評価の有効性と課題に関する考察」国際協力研究Vol.23No.1 2008年1月「JICA技術協力プロジェクトの有効性と課題」国際開発研究通巻17-2号 2013年7月『グローバル人材に贈るプロジェクトマネジメント』 [共著: 単行本] 関西学院大学出版会 2016年1月PCM ハンドブック(モニタリング・評価編) NPO法人PCM Tokyo監修 2016年12月 「ザンビアにおける農業普及サービスの効果に関する一考察 : 経済的効果と心理的効果 」国際農林業協力 Vol.39 No.3(通巻184号) 2018年1月 「地域おこし協力隊が農山村地域の再生に与える影響について」(共著)文京学院大学総合研究所 紀要第18号 pp1-13 2020年9月『プログラム評価ハンドブック』(第8章質的調査の方法) |
| 資格等 | プロジェクト・マネジメント・プロフェッショナル(米国Project Management Institute認定) 評価士(日本評価学会認定) |